|
連載「子どもと音楽」(13)
「勇気」と「自信」をはぐくむこと
|
|
幼児は、生来的に意欲に満ちた存在です。その意欲は遊びや生活のさまざまな場面で発揮されますが、とりわけそこでの大人の役割は、意欲的に遊びに取り組むことができるように、環境を整えることでしょう。子どもが安心して過ごせる空間は“意欲を吹き出す土壌”となります。子どもは、この安心できる空間を基地として、さまざまな興味や関心を開花させ、いま持てる感覚を駆使して自分の想いを膨らませるのです。つまり、“安心”はさまざまな経験を可能にさせてくれる空間となるのです。そして、そこで意欲が生まれ、チャレンジ精神の芽や、やさしさや思いやりの芽が育まれていくのだと考えられます。
しかし、その空間では、大人が「子どもに良かれ」と思ってしていることが、実際には子どもにとって大きな障害になっていることも少なくありません。たとえば、子どもがボタンをはめようとして苦闘している姿をみかねて、思わず手を出してしまう大人は、子どもの学習機会(チャレンジの機会)を奪っていることに気づかないでいる。別な例で−。子どもが教師の仕向けたゲームに参加し、いざゲームを終えた瞬間に「ねえ先生、もう遊んでいいの?」と素直に心中を告げる−これは衝撃的です。子どもは明らかに自分のやりたい事柄(主体的に取り組むこと)を持っている。この例の場合は、子どもの意欲をうまく汲み取れないでいる大人がそこにいる。
子どもの意欲や意志を最大限に尊重することは、子どもの主体的な態度と責任感、チャレンジする勇気や粘り強さを育む原動力となるのです。同時に、その遊びが周囲に及ぼす影響にも配慮しなければなりません。その気くばりの中で、我慢することや他者と共存することの大切さ、秩序の快感なども経験するでしょう。
意欲に溢れた子ども、なんて輝いている存在でしょう。子どもたちの日々の生活は、未知なることに対する小さな勇気の連続でもあります。その小さな勇気を励まし、大きな勇気に育てていきたいものです。
|
CHC通信第26号(2001年12月) 発行:CHC音楽教室
|
| 連載「子どもと音楽」(14)
シアトルで感じたこと
|
昨年の8月上旬、私は米国ワシントン州シアトル市を訪れた。その地はアメリカで一躍有名になったイチローが活躍するシアトル・マリナーズの本拠地でもある。私の目的はリトミック講座(1週間)に参加することであった。アメリカの夏は実に過ごしやすい。日本で38度の猛暑が続いていた同じ頃、シアトルは20度前後で、湿度の低い気候であった。実に快適だった。その地で終日、音楽(リトミック)することができるというのは、実に幸せなことだと思った。
シアトルでは、ジュリア・ブラック女史(ワシントン大学教授)の主宰するリトミック協会がある。この年、講座には全米各地から約30名の参加者が集った。私もその一人。参加者は、小学校や幼稚園の教師、ピアノレスナー、学生など、さまざま。年齢も20代から50代まで幅広い。講座は、動きを中心に様々な音楽の学習を行った。身体の柔軟(ウオームアップ)、基本的なリズムの動き、ピアノの即興演奏、子どものためのリトミック教授法等など。連日の研修はとても楽しかった。その内容は、日本のそれと較べて、ほとんど異質とは感じなかった。
しかし、ここでの体験で私が最も興味深く感じたことは、参加者が実に多様で、表現力に富んでいることであった。むしろ音楽的な能力(聴取力や演奏力など)は日本人の方が繊細で優れているかもしれないと思った。が、自分自身の感じたことや考えを伝えようとするパワーは、遥かに強くエネルギッシュであった。音楽表現は稚拙であっても、心に秘められたエネルギーを押し出そうとするパワーに私は圧倒された。逞しくもあった。そのような力は、どのようにして培われるのだろうか。
一つには、多言語社会の中で他者と関わり生きていくために不可欠な能力として、自然に培われたものなのだろうとも思った。私にはまだ「これだ」と思える答えは得られていないが、一つ思い当たることは、現代日本の子どもたち(そして私たち大人も)に足りないものは、このあたりの「内なるパワー」にあるのではないかと思われた。リトミックの体験が、このような内なるエネルギーのわき出る空間としたい。このような思いを強くもったシアトルの一夏であった。 |
| CHC通信第27号(2002年4月) 発行:CHC音楽教室 |
連載「子どもと音楽」(15) |
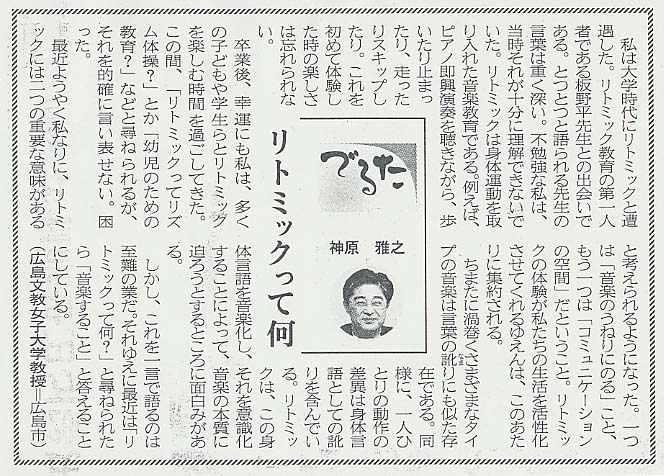 |
| 中国新聞(2002年4月23日夕刊第1面) |