|
今回は、幼児が「楽しい」と感じられる音楽レッスンを展開するために、大人はどのような配慮が必要なのか考えてみたいと思います。
1.砂場遊びと音楽、その共通するもの
私は、子どもたちが砂遊びに夢中で取り組んでいる姿を見るとき、その姿は同時に音楽に熱中しているときの姿と重なり合って見えてきます。砂遊びに夢中の子どもは、心の中で「この部分の砂をこうして、あの部分を掘って〜」など、自分なりの完成モデルがしっかりと描いているのだと思われます。そして、製作途中でも随時そのモデルを変更しながら、より洗練された面白い作品に仕上げていくのです。その試行錯誤している時間(過程)が楽しいのです。
砂場遊びと同じように、音楽(歌唱・演奏・動きなど)している時に、自分なりのアイデアを注ぐことができれば、それは楽しい時間になっていくことでしょう。そうした「楽しい」遊びの時間を持つためには、いくつかの要件が必要です。
第1点は、子ども自身がこれから展開されるであろう遊びの「見通し」を持てること。遊びや活動の行方が自分なりにイメージできて、その流れに身を委ねているときが愉しい時間なのです。そして、多くの場合、見通しがつくようになる前に(いきなり参加するのではなくて)傍観の時間(観察の時間)や、周囲の人の取り組みを自分なりに試してみる場面も必要なのです。つまり、身体の動きとして表される前に、まず始めに「心」が先行して動き始めるのです。 外からは“見えにくい子どもの心が見える”ようになる。これはレッスンを楽しくするための最初のキーポイントになるでしょう。
第2点は、レッスンでは「自分のできることで参加する」こと。“私にはできない”と思われるような内容に対して、子ども達はなかなかチャレンジしてみようという気持ち(勇気)が湧いてこないようです。“私にも出きるかもしれない”と思われるときに、レッスンに対して興味関心が湧いてくるのです(その結果、うまく出来たり、あるいは出来なかったりするのです)。その一方で、“つまらない”と感じられるときは、あまりに難しかったり、あるいは既に獲得した内容のものであったりします。リトミックにおいても、このあたりの子どもの気持ちを読みとりながら、“自分もチャレンジしてみよう”と思えるような内容に、遊びを調節することは肝心なことです。
2.部分よりも全体
例えば、家を建てるとき、私たちはまず建物全体をイメージし、その後で玄関の形や装飾品の色合いなど、細かな部分を考えます。そして再び全体に目を向けるのです。つまり、全体と部分は常に切り離せない関係にあります。教育においても、同じような関係を読みとることができます。
例えば、一般的に大人は、歌を歌ったり、ピアノを演奏したり、作曲したりなど、既に形式化された表現モードとして、音楽活動を捉える傾向があるようです。その発想からは、つい「ドレミが判らないからピアノが弾けない」とか「楽譜が読めないから音楽は作れない」などと考えてしまうのです。しかし、その一方で、カラオケで歌うときは「楽譜が読めないから歌えない」とは言わない(例えば、演歌を譜面通りに歌ったのでは味気ないものになってしまう。それを知っている大人はその曲の情緒性に心を注いで歌うのです)。
このように、私たちは「学習」を考えるとき、全体を見ることよりも部分に目を奪われ易いように思われます。学習は、まず全体を把握することが優先されるべきなのです。
3.総合化すること
前述のように「音楽する」とき、誰も最初は楽譜が読めないし、ドレミも知らないのです。そうであっても「音楽に参加する」ことはできます。自分の出来ること、つまりスウィングしたり、手を叩いたりしながら、音楽に身を委ねることができるのです。リトミックが楽しいと感じられるのは、このあたりにあります。
こうしてリトミックでは、「自分の出きること」を手がかりにして、あたかも芸術家になったかのような、身も心も音楽に浸っている時間を味わいたいのです。このセンスを、イギリスの音楽教育研究家であるスワンウィックは「マスタリー」と呼んでいます(注参照)。つまり、ある時はあたかも作曲家(創る人)になったかのように口ずさみ、ある時は聴衆となって音に聴き入り、またある時は演奏家(表現する人)として演じるのです。このように、様々な役割を総合的に経験することが、幼い時期の音楽経験では特に強調されてよいでしょう。ここでも遊びのセンスが大いに発揮されることになります。
これを前述の砂場遊びにたとえるなら、仲間と話しあいながら構想を練り(創る人)、砂をいじったり(表現者)、休んだりしながら(聴衆)完成に近づいていく。このように、いろいろな立場を巡りながら、遊びは少しずつ発展されていくのです。まさにマスタリーの世界は、総合的にものごとを捉える学習空間なのです。
加えて、幼児はリトミックする中で、(自分のできることを通して)存在をアピールしたり、相手の存在(他者の思い)を認めたりすることも貴重な体験となります。つまり、物語遊びやリズミカルなゲームを通して、人との関わりを楽しむことも「楽しいレッスン」作りに欠かせない要件となるでしょう。
音楽的センスと人間相互の関係作り−この2点を総合的にやわらかく包み込んでいるのがまさに「遊び」のセンスなのです。リトミックが「遊び」と感じられる雰囲気、これは幼児の活動を考える上で特に重要なポイントとなるでしょう。
(注)スワンウィック,K.,野波健彦ほか訳『音楽と心と教育』音楽之友社,1992,p.91
リトミック通信第68号(リトミック研究センター発行、1999/11/1)
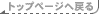
|